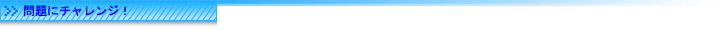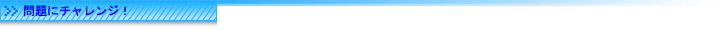|
 |
問題 |
解説 |
 |
 |
 |
【問1】
次の10進小数のうち,2進数で表すと無限小数になるものはどれか |
|
Ans:0.05
2進数に基数変換してみよう
|
 |
|
| 【問2】
2進数の101.11を10進数で表したものはどれか。 |
|
Ans:5.75
101.112=4+1+0.5+0.25=5.75
|
|
【問3】
ある整数値を,負数を2の補数で表現する2進表記法で表すと最下位2ビットは“11”であった。10進表記法のもとで,その整数値を4で割ったときの余りに関する記述として,正しいものはどれか。ここで,除算の商は,絶対値の端数が切り捨てられるものとする。 - その整数値が正であれば3
- その整数値が負であれば3
- その整数値が負であれば−3
- その整数値の正負にかかわらず0
|
|
Ans:1.その整数値が正であれば3
この整数値の3ビット目以上の値は必ず4で割り切れる(3ビット目の数値は22の倍数)。したがって最下位2ビット“11”、すなわち3が4で割ったときの余りとなる。ただし、この整数値が負であったとすると、“11”の部分も2の補数表記されていることになるためこの限りではない。 |
|
【問4】
数値の部分が6けたの符号付き10進数を,パック10進表記法で表すと,必要なバイト数は幾らか。 |
|
Ans:4
パック10進数は1バイトで2桁の10進数を表し、符号は最下位桁の4ビットに付加する |
|
【問5】
浮動小数点演算において,値の近い数値の減算で有効数字のけた数が減る現象はどれか。 |
|
Ans:けた落ち
打切り誤差:計算処理が冗長になる前に一定の規則で打ち切る場合に生じる誤差
情報落ち:絶対値の大きさに極端な差がある値の演算時に指数をそろえるため、数値のビット情報が欠落すること
丸め誤差:四捨五入、切り上げ切り捨てなど。 |
|
【問6】
8ビット符号のうち,0と1のビット数が等しいものは幾つあるか。 |
|
Ans:70
8ビット符号で0と1のビット数が等しいのは、それぞれが4ビットのとき。すなわち、8P4÷4P4となる。 |
|
【問7】
n個のデータをバブルソートを用いて整列するとき,データ同士の比較回数は幾らか |
|
Ans:n(n-1)/2
交換しない場合も比較は行われることに注意しよう |
|
【問8】
電気信号によってデータの書換え,消去が可能なメモリであり,電源を切っても内容を保持できるものはどれか。 |
|
Ans:フラッシュメモリ
名前からわかるように、DRAM、SRAMはRAM(電源を切ると記憶内容は消えてしまう)。マスクROMは書き換え不可 |
|
【問9】
SRAMの記憶セルに使用され,二つの安定状態をもつ回路であり,順序回路の基本構成要素となるものはどれか。 |
|
Ans:フリップフロップ
SRAMはフリップフロップ回路で構成される。フリップフロップ(flip-flop)には「パタパタ」という意味もある。回路内部で0か1かの状態を保ちつづけることができるので、リフレッシュ(再書き込み)が必要ない。
|
|
【問10】
命令の構成に関する記述のうち,適切なものはどれか。 - オペランドの個数は,その命令で指定する主記憶の番地の個数と等しい
- コンピュータの種類によって命令語の長さは異なるが,一つのコンピュータでは,命令語の長さは必ず一定である
- 命令語長が長いコンピュータほど,命令の種類も多くなる
- 命令は,命令コードとオペランドで構成される。ただし,命令の種類によっては,オペランドがないものもある
|
|
Ans:4.命令は,命令コードとオペランドで構成される。ただし,命令の種類によっては,オペランドがないものもある
オペランド(アドレス部)のない命令(0アドレス命令)も存在する
|
|
【問11】
50MIPSの処理装置がある。この処理装置の平均命令実行時間は幾らか。 |
|
Ans:20ナノ秒
MIPS(Million Instructions per Second ; 百万命令/秒)の意味を考えよう。
|
|
【問12】
処理装置で用いられるキャッシュメモリの使用目的として,適切な記述はどれか。 - 仮想記憶のアドレス変換を高速に行う
- 仮想記憶のページング処理を高速に行う
- 主記憶へのアクセス速度とプロセッサの処理速度の差を埋める
- 使用頻度の高いプログラムを常駐させる
|
|
Ans:3.主記憶へのアクセス速度とプロセッサの処理速度の差を埋める
プロセッサの処理速度は主記憶へのアクセス速度とくらべると非常に早い。この時間差を埋めるためのメモリがキャッシュメモリである。
|
|
【問13】
主記憶装置の高速化の技法として,主記憶を幾つかのアクセス単位に分割し,各アクセス単位をできるだけ並行動作させることによって,実効的なアクセス時間を短縮する方法を何というか。 |
|
Ans:メモリインタリープ
CPUは主記憶に連続的にアクセスすることが多いが、主記憶の素子へのアクセスにはわずかな待ち時間が必要である。するとこの待ち時間分が無駄になってしまうので、素子をバンクと呼ばれるいくつかの単位に分割し、これに次々とアクセスすることによって待ち時間を短縮する(メモリインタリーブ方式)。
|
|
【問14】
回転速度が5,000回転/分,平均シーク時間が20ミリ秒の磁気ディスクがある。この磁気ディスクの1トラック当たりの記憶容量は,15,000バイトである。このとき,1ブロックが4,000バイトのデータを,1ブロック転送するために必要な平均アクセス時間は何ミリ秒か。 |
|
Ans:29.2
ディスクが1回転するのにかかる時間は60(秒)÷5000(回転)=0.012よって12ミリ秒。この間に15,000バイト記憶されているので、4000バイトのデータ転送にかかる時間は約3.2ミリ秒。また、平均サーチ時間は12÷2=6ミリ秒。平均シーク(位置決め)時間は20ミリ秒であるので、これらを合計すればよい。
|
|
【問15】
磁気ディスク装置の仕様のうち,回転待ち時間に直接影響を及ぼすものはどれか。 |
|
Ans:単位時間当たりのディスク回転数
回転待ち時間(サーチ時間)は回転時間÷2である
|
|
【問16】
CD−Rに関する記述のうち,適切なものはどれか。 - CD−ROM装置では読み出せない
- CD−ROMより大容量のデータが書き込める
- 初期化することによって,再書込みが可能となる
- 複数の書込み方式がある
|
|
Ans:4.複数の書込み方式がある
CD-Rは、CD-ROM装置で読むことが可能な媒体で、記憶容量はCD-ROMと同じ。再書き込みが可能であるのはCD-RWである
|
|
【問17】
RAID0の説明として,適切なものはどれか。 - 高価ではあるが信頼性の高い磁気ディスクを複数台制御し,主として大容量化を目指している
- 細分化したデータを複数の磁気ディスクに巡回的に並列入出力することによって,転送速度の向上を図っている
- 冗長な磁気ディスクを必要とせず,各ブロックごとにCRCによるエラー訂正を行っている
- 廉価な複数の磁気ディスクで構成し,OSによる制御で信頼性と高性能化を図っている
|
|
Ans:2.細分化したデータを複数の磁気ディスクに巡回的に並列入出力することによって,転送速度の向上を図っている
RAID0はデータを複数のディスクに分散してさせることで、データの読み書きを並列的に行い、主として高速化をはかる方式である。
|
|
【問18】
EIA(米国電子工業会)が定めた,データ通信システムにおけるデータ端末装置と,モデムなどのデータ回線終端装置との間の物理インタフェースの規格はどれか。 |
|
Ans:RS-232C
他の選択肢はEIA以外の機関が規格化したもの。例えばSCSIの規格はANSIによる
|
|
【問19】
プロセッサは演算装置及び制御装置からなる。制御装置に含まれる要素はどれか。 |
|
Ans:命令デコーダー
命令デコーダは制御装置に含まれ、命令後の命令部を解読(デコード)する
|
|
【問20】
仮想記憶におけるセグメンテーション方式とページング方式に関する記述のうち,ページング方式の特徴はどれか。 - 仮想アドレス空間の管理単位である領域の大きさを,実行時に動的に変更できる
- 実記憶領域の利用効率が高く,領域管理も容易である
- プログラムからみた論理的な単位でアクセス保護を行うことができる
- プログラム実行中のモジュールの取込みや共有を容易に行うことができる
|
|
Ans:2.実記憶領域の利用効率が高く,領域管理も容易である
ページング方式では、単純に一定の大きさ(2〜4KB程度)にプログラムを分割する。一方セグメンテーション方式では、大きさを論理的なまとまりごとに分割する。
|
 |