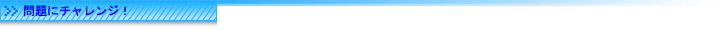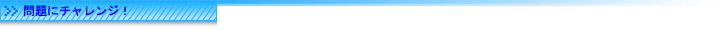|
 |
問題 |
解説 |
 |
 |
| |
【問1】
10進数の演算式7÷32の結果を2進数で表したものはどれか |
|
Ans:0.00111
32は25なので、式7÷32の結果を2進数で表したものは、7を2進数で表した値111の小数点を左に5つ移動したものになる。 |
|
|
| 【問2】
次の式は、何進法で成立するか。
1015÷5=131(余り0) |
|
Ans:7
n進数の整数部のm桁目は、10進数では、nの(m-1)乗の重みを持つ。従って、1015が1~4の選択肢の進法であるとすると、その値を10進数で表した値はそれぞれ、
・1×63+0×62+1×61+5×60
・1×73+0×72+1×71+5×70
・1×83+0×82+1×81+5×80
・1×93+0×92+1×91+5×90
問題の式は、5で割ったときの余りが0であるので、項目2か項目3が正解であることがわかる。項目2、項目3の式を5で割るとそれぞれ次のようになる。
・355÷5=71=131(7)
・525÷5=105=151(8) |
|
【問3】
実数aをa=f×r eと表す浮動小数点表記に関する記述として、適切なものはどれか。 - fを仮数、eを指数、rを基数という
- fを基数、eを仮数、rを指数という
- fを基数、eを指数、rを仮数という
- fを指数、eを基数、rを仮数という
|
|
Ans:1.fを仮数、eを指数、rを基数という
浮動小数点表記では、数値を次のような形式で表します。
(仮数)×(基数)指数 |
|
【問4】
32ビットのレジスタに16進数ABCDが入っているとき、2ビットだけ右に論理シフトしたときの値はどれか |
|
Ans:2AF3
1桁の16進数は4桁の2進数で表すことが出来る。
ABCD(16)=1010101111001101(2)
この値を2ビット右に論理シフトすると、
0010101011110011(2)=2AF3(16)
となる。 |
|
【問5】
桁落ちの説明として、適切なものはどれか - 値がほぼ等しい浮動小数点同士の減算において、有効けた数が大幅に減ってしまうことがある
- 演算結果が、扱える数値の最大値を超えることによって生じる誤差である
- 数表現のけた数に限度があるとき、最小のけたより小さい部分について四捨五入、切上げ又は切捨てを行うことによって生じる誤差である
- 浮動小数点の加算において、一方の数値の下位のけたが欠落することである
|
|
Ans:1.値がほぼ等しい浮動小数点同士の減算において、有効けた数が大幅に減ってしまうことがある
桁落ちとは、絶対値の近い浮動小数点どうしを減算したときに、結果の有効数字が少なくなってしまう現象のことである。
2 オーバーフローの説明
3 打切り誤差の説明
4 情報落ちの説明 |
|
【問6】
赤、白、黄の 3 種類の球が 3 個ずつ入っている箱の中から、3 個の球を同時に取り出すとき、すべて白の球になる確率は幾らか |
|
Ans:1/84
箱の中には赤、白、黄の3種類の球が3個ずつ合計9個入っている。9個の中から3個の球を同時に取り出すときに考えられる組み合わせの数は
9C3=(9×8×7)/(3×2×1)=84
通り存在する。このうち、すべてが白の球になる組み合わせは1通りしかないので、求める確率は1/84である。 |
|
【問7】
関数eq(X, Y)は、引数XとYの値が等しければ1を返し、異なれば0を返す。整数A,B,Cについて、eq(eq(A, B), eq(B, C))を呼び出したとき、1が返ってくるための必要十分条件はどれか |
|
Ans:(A=BかつB=C)又は(A≠BかつB≠C)
eq(eq(A,B),eq(B,C))が必要十分条件はeq(A,B)とeq(B,C)が等しいことである。これには、次の2つの場合が考えられる。
(1)eq(A,B)=1、eq(B,C)=1
この場合は、A=BかつB=Cとなる。
(2)eq(A,B)=0、eq(B,C)=0
この場合は、A ≠ B かつ B ≠ Cとなる。
従って、(A = B かつ B = C) 又は (A ≠ B かつ B ≠ C)が、eq(eq(A,B),eq(B,C))が1を返すための必要十分条件となる |
|
【問8】
2 種類の文字 "A","B" を 1 個以上、最大 n 個並べた符号を作る。60 通りの符号を作るときの n の最小値は幾らか |
|
Ans:5
文字A,Bをn個並べたとき、表せる符合の数は、2n通りとなる。従って、60通りの符号を表すnの最小値は、
21+22+23+24+25=62
より、5であることがわかる。 |
|
【問9】
A,B,C,D の順に到着するデータに対して、一つのスタックだけを用いて出力可能なデータ列はどれか |
|
Ans:C,B,D,A
スタックは後入先出(Last In First Out; LIFO)と呼ばれるデータ構造で、最後に格納したデータが先に取り出される。
1.最初にAを出力していることから、Aをスタックに格納して、Bが到着する前にすぐ取り出したことがわかる。Aの後でDを出力していることから、Aを取り出した後は到着後(B→C→D)に格納したことがわかる。従って、Dの後にはCが出力されるはずだが、そうなっていないため、このデータ列は出力可能でないことがわかる。
2.最初にBを出力していることから、A,Bをスタックに格納して、Cが到着する前にBをすぐ取り出したことがわかる。Bの後でDを出力していることから、Bを取り出した後は到着順(A→C→D)に格納したことがわかる。従ってDの後にはCが出力されるはずであるがそうなっていない。
3.最初にCを出力していることから、A,B,Cをスタックに格納して、Dが到着する前にCをすぐ取り出したことがわかる。Cの後でBを出力し、その後にDを出力していることから、C,Bを取り出した後は到着順(A→D)に格納したことがわかる。このため、Dの後にはAが出力される。従って、このデータ列は出力可能。
4.最初にDを出力していることから、A,B,C,Dをスタックに格納して、Dを取り出したことがわかる。従ってCの後にはBが出力されるはずだが、そうなっていない。 |
|
【問10】
16 進数で表される 9 個のデータ 1A,35,3B,54,8E,A1,AF,B2,B3 を順にハッシュ表に入れる。ハッシュ値をハッシュ関数 f(データ) = mod(データ,8) で求めたとき、最初に衝突が起こる(既に表にあるデータと等しいハッシュ値になる)のはどのデータか。ここで、mod(a,b) は a を b で割った余りを表す。 |
|
Ans:B2
2桁の16進数をcdとすると、10進数では、
c×161+d×160=c×16+d
と表される。c×16は必ず8で割り切れるため、cdを8で割った余りは、cの値によらず、dの値のみで決まることがわかる。従って、9個のデータの余りは順に、
2,5,3,4,6,1,7,2,3
となる。このことから、最初に衝突が起こるのは、8番目に入れるデータであるB2であるとわかる。 |
|
【問11】
非負の整数 n に対して次のとおりに定義された関数 F(n),G(n) がある。F(5) の値は幾らか。
F(n) : if n ≦ 1 then return 1 else return n × G(n-1)
G(n) : if n = 0 then return 0 else return n + F(n-1) |
|
Ans:65
5>1であるので、
F(5)=5×G(4) =5×(4+F(3)) =20+5×(3×G(2)) =20+15×(2+F(1)) =20+30+15×1 =65従って、F(5)の値は65となる。 |
|
【問12】
フリップフロップ回路を利用した高速なメモリはどれか |
|
Ans:SRAM
フリップフロップ回路は、信号を与えることで状態の切り替えができる、2つの安定状態を持つ回路。この回路を利用した高速なメモリはSRAMで、データの読み書きが出来るRAMのひとつである。DRAMに比べてアクセス速度が速く、消費電力も少ない反面、容量当たりの製造コストが高いので、CPUのキャッシュメモリに利用される。 |
|
【問13】
アドレス指定方式のうち、命令読出し後のメモリ参照を行わずにデータを取り出すものはどれか |
|
Ans:即値オペランド
命令のアドレス部がそのまま処理する対象(オペランド)となっており、命令の読み出し後、メモリ(主記憶)へのアクセスを行う必要のないアドレス指定方式は、即値オペランド(即値アドレス)方式。 |
|
【問14】
50MIPSの処理装置の平均命令実行時間は幾らか |
|
Ans:20ナノ秒
MIPS(Millions of Instructions Per Second)は、コンピュータの処理能力を表す単位で、1秒間に何百万回命令を実行できるかを示す。
問題のコンピュータの1命令当たりの平均命令実行時間は、
1(秒)÷50(百万命令)
=1(秒)÷50,000,000(命令)
=1,000,000,000(ナノ秒)÷50,000,000(命令)
=20(ナノ秒/命令)
となる。 |
|
【問15】
アクセス時間の最も短い記憶装置はどれか |
|
Ans:CPUのレジスタ
記憶装置をアクセスが高速な順に並べると、
CPUのレジスタ>CPUのキャッシュメモリ>主記憶>磁気ディスク
となる。従って、アクセス時間がもっとも短いのはCPUのレジスタである。 |
|
【問16】
回転数が4,200回/分で、平均位置決め時間が5ミリ秒の磁気ディスク装置がある。この磁気ディスク装置の平均待ち時間は約何ミリ秒か |
|
Ans:12
平均待ち時間は、次の式で計算します。
平均待ち時間=平均位置決め時間+平均回転待ち時間
平均回転待ち時間は、1回転に要する時間÷2で求めるので、
1(回)÷4,200(回/分)×60(秒/分)÷2
≒0.007(秒)=7(ミリ秒)
となる。従って、平均待ち時間は、
5(ミリ秒)+7(ミリ秒)=12(ミリ秒)となる。 |
|
【問17】
RAIDに関する記述のうち、適切なものはどれか
- 1台のディスク装置で、ソフトウェアによって、磁気ディスクの信頼性の向上を図っている
- ストライピングの技術を利用して、アクセスの高速化を図っている
- ディスクキャッシュの技術を利用して磁気ディスクの信頼性の向上を図っている
- ミラーリングの技術を利用して、アクセスの高速化を図っている
|
|
Ans:2.ストライピングの技術を利用して、アクセスの高速化を図っている
RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)とは、複数の記憶装置を用いて、全体を1つの記憶装置のように制御する仕組みのことで、0から5までの6段階のレベルがある。RAID0は、データを複数の磁気ディスクに分散して高速化を図る方式で、ストライピングと呼ぶ。 |
|
【問18】
パソコンでの記憶媒体のフォーマット処理に関する記述のうち、適切なものはどれか
- 磁気ディスクでは、物理フォーマットの処理に先立って、論理フォーマットを行う必要がある
- 物理フォーマットでは、磁気ディスク上にパーティションを作成し、装置として認識可能にする
- 論理フォーマットでは、OS固有のファイルシステムの管理領域や実際に記憶されるデータの論理的な位置を設定する
- 論理フォーマットでは、不良セクタの検査を同時に行う。エラー発生時には予備領域内の正常なセクタを不良セクタの代替とすることができる
|
|
Ans:3.論理フォーマットでは、OS固有のファイルシステムの管理領域や実際に記憶されるデータの論理的な位置を設定する
フォーマットとは、記憶媒体の記録形式を初期化し、実際に記録できるようにすることである。フォーマットでは、まず物理フォーマットを行い、ディスク上のトラックをセクタに分割することで、コンピュータからディスクを制御することを可能にする。次に論理フォーマットを行い、分割されたセクタにブロック番号を割り当てることで、OS固有のファイルシステムの管理領域や実際に記録されるデータの論理的な位置を設定します。 |
|
【問19】
周辺機器との接続インターフェースであるIEEE1394とUSBの両方に共通する特徴はどれか
- コンピュータや機器の電源を入れたままでも、機器の着脱が可能である
- 最大転送速度が、10Mビット/秒である
- 接続する機器ごとに、重複しないIDを設定する必要がある
- 複数のデータ線をもち、転送方式がパラレル転送である
|
|
Ans:1.コンピュータや機器の電源を入れたままでも、機器の着脱が可能である
IEEE1394は、高速なデータ転送が可能なシリアルインターフェース仕様で、USBは、最大127台の周辺機器を、ハブを使ってツリー状に接続できるシリアルインターフェース。両方のインターフェースとも、パソコンの起動中に自由に抜き差しできるホットプラグインやプラグアンドプレイに対応しているという特徴がある。 |
|
【問20】
液晶ディスプレイの説明として、適切なものはどれか。
- 電極の間に電気を通すと発行する特殊な有機化合物を挟んだ構造のディスプレイである
- 電子銃から発射された電子ビームが発光体に当たり発光することを利用するディスプレイである
- 光の透過を画素ごとに制御し、カラーフィルタを用いて色を表現するディスプレイである
- 放電によって発生する紫外線と蛍光体を利用するディスプレイである
|
|
Ans:3.光の透過を画素ごとに制御し、カラーフィルタを用いて色を表現するディスプレイである
液晶ディスプレイは、表示装置に液晶を用いたディスプレイ。液晶は電圧によって光の透過度が変化するため、画素ごとに光の透過度を制御し、カラーフィルタを用いて色を表現する。なお、液晶ディスプレイは、液晶ディスプレイ自体が発光しないため、液晶板の裏から光を照らす仕組みが必要である。
その他の解答群はそれぞれ、
1.有機ELディスプレイ
2.CRTディスプレイ
4.プラズマディスプレイ の説明である。 |
 |