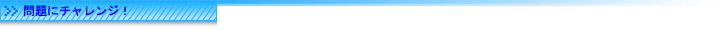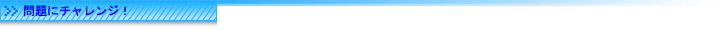|
 |
問題 |
答えを選ぶ |
正否 |
 |
 |
| |
【問1】
ブラックボックステストにおけるテストデータ作成方法として,適切なものはどれか。
- 機能仕様から同値クラスや限界値を識別し,テストデータを作成する。
- 業務で発生するデータの発生頻度を分析し,テストデータを選定する。
- 入力可能なデータを無作為に抽出し,テストデータとする。
- プログラム処理の流れ図から,分岐条件に基づきテストデータを作成する。
|

|
|
|
|
【問2】
レグレッション(退行)テストの説明として,適切なものはどれか。
- 修正した内容が今まで正常に動作していたほかの機能に影響を与えていないことをテストすること
- 操作性の良さや表示されるメッセ−ジの分かりやすさをテストすること
- データ量を増やしたり,何人もの人で同時に処理要求を行ったりしても,業務に支障がないことをテストすること
- 間違ったデータを入力したときにエラーとして認識されることをテストすること
|

|
|
|
【問3】
システム開発におけるテストでは,小さな単位から大きな単位へ,テストを積み上げていく方法が採られることが多い。このとき,テストの適切な実施順序はどれか。
- システムテスト → 結合テスト → 単体テスト
- システムテスト → 単体テスト → 結合テスト
- 単体テスト → 結合テスト → システムテスト
- 単体テスト → システムテスト → 結合テスト
|

|
|
|
【問4】
リスク分析に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 考えられるすべてのリスクに対処することは,時間と費用がかかりすぎるので,損失額と発生確率を予想し,リスクの大きさに従って優先順位をつける。
- リスク分析によって評価されたリスクに対し,すべての対策が完了しないうちに,繰り返しリスク分析を実施することは避けるべきである。
- リスク分析は,将来の損失を防ぐことが目的であるから,過去の類似プロジェクトの経験から作成されたデータでは役に立たない。
- リスク分析は,リスクの存在と発生による損失額を知ることが目的であり,その対策に要する費用については考慮しなくてもよい。
|

|
|
|
【問5】
サーバ上で稼動するアプリケーションプログラムが使用するデータのバックアップ処理に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アプリケーションプログラムの稼動状況と無関係に,毎日定刻に行う。
- サーバの運用管理者の都合の良い時刻に行う。
- サービスレベルを低下させないように,アプリケーションプログラムを稼動したまま行う。
- バックアップ処理中のデータ更新を避けるため,アプリケーションプログラムを停止させてから行う。
|

|
|
|
【問6】
ディスク障害が発生したときのデータベース復旧のために,ある時点のデータベースの内容をコピーして保存しているファイルはどれか。 |

|
|
|
【問7】
データベースファイルの排他制御に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- あるプログラムによって共有ロックがかけられている資源に対して,別のプログラムから共有ロックをかけることは可能である。
- あるプログラムによって共有ロックがかけられている資源に対して,別のプログラムから占有ロックをかけることは可能である。
- あるプログラムによって占有ロックがかけられている資源に対して,別のプログラムから共有ロックをかけることは可能である。
- あるプログラムによって占有ロックがかけられている資源に対して,別のプログラムから占有ロックをかけることは可能である。
|

|
|
|
【問8】
8けたの口座番号のうち,右端の1けたをチェックディジットとする。このチェックディジットの値は,何によって決まるか。
- 口座の種類
- 口座番号の右端の1けたを除いた7けた
- 顧客の月間取引高
- 個人顧客か法人顧客かの区分
|

|
|
|
【問9】
ユーザ部門が起票した入力原票を,運用部門がデータ入力する場合,運用部門の処理に関する記述として,適切なものはどれか。
- 入力原票1件ごとの入力結果の確認は,処理結果リストをユーザ部門に送付し,ユーザ部門が行うことにしている。
- 入力原票の記入内容に誤りがある場合は,誤り内容が明らかなときに限りオペレータの判断で入力原票を修正し,入力処理している。
- 入力原票は処理期日まで運用部門の受付者がそれぞれ保管し,到着の有無,受領枚数の点検などの授受確認は,処理期日直前に一括して行うことにしている。
- 入力済みの入力原票は,不正使用や機密情報の漏えいなどを防止するために,入力後直ちに廃棄することにしている。
|

|
|
|
【問10】
分散環境におけるデータ管理に関する記述として,適切なものはどれか
- 操作ミスによるデータの破壊を防ぐために,更新を行うのは特定のユーザに限定する必要がある。
- データ管理に不慣れなユーザも存在するので,分散管理であっても個別管理は行わず,ホスト集中型と同じ手順・体制による集中管理が必要である。
- 廃棄したデータに関しては,注意が払われないことがあるので,統一した廃棄手順を決めて管理を徹底する必要がある。
- ユーザの自己管理が前提であり,専任のデータ管理者は不要である。
|

|
|
|
【問11】
サーバへのアクセスを希望する人にまずユーザIDと仮パスワードを与えた。パスワードを変更する画面を設計するとき,ユーザに求められる入力の順序のうち,最も適切なものはどれか。
- 仮パスワード → 新パスワード → 新パスワード → ユーザID
- 新パスワード → ユーザID → 仮パスワード → 新パスワード
- ユーザID → 仮パスワード → 新パスワード → 新パスワード
- ユーザID → 仮パスワード → 新パスワード → ユーザID
|

|
|
|
【問12】
電源の瞬断に対処したり,停電時にシステムを終了させるのに必要な時間だけ電源供給することを目的とした装置はどれか。 |

|
|
|
【問13】
見やすいドキュメントを作成するための,円グラフの使用法として,適切なものはどれか。
- 構成比・内訳などを示すときに用い,基本的に構成比の高い項目順に記載する。
- 項目数が多くなりすぎたり,大分類と小分類のように項目の中で更に分類したりする場合には,半円グラフを用いる。
- 年度別の業績など,対象となる項目が推移していくプロセスを示すときに用いる。
- 輸出と輸入など,二つの項目を対比させたい場合には,二重円(ドーナツ)グラフを用いる。
|

|
|
|
【問14】
ワープロソフトの禁則処理について説明しているものはどれか。
- 英単語の途中で改行するときに,適切な位置で自動的に−(ハイフン)を付けて次行につなげる。
- 特定の文字(,。¥$など)が行頭又は行末にならないように行の割付けを行う。
- 入力を間違えた文字を自動的に修正する。
- マクロの機能を一時中断する。
|

|
|
|
【問15】
ソフトウェアの開発及び保守におけるドキュメント作成に関する記述のうち,最も適切なものはどれか。
- 箇条書きによる記述や図表を用いると意味・内容が不明確になるので,極力自然言語による文章で表現する。
- ドキュメント間の関連性が明確になっていることが重要であり,これによってドキュメントごとの内容に関する整合性チェックが行え,品質向上につながる。
- ドキュメントの記述内容の重複や冗長性は,ソフトウェアの保守性だけでなく,ドキュメントの保守性を向上させるために必要である。
- ドキュメントの記述は,保守担当者よりも開発者に理解できることを最優先として,あまり時間をかけずに生産性を向上させることが望ましい。
|

|
|
|
【問16】
非常に大きな数を素因数分解することが困難なことを利用した公開かぎ暗号方式はどれか。
|

|
|
|
【問17】
アクセス権をもつ端末であることを確認するために,回線をいったん切り,システム側から再発信して通信を開始する方法はどれか。 |

|
|
|
【問18】
認証局(CA)の役割に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 相手の担保能力を確認する。
- 公開かぎ暗号方式を用いて,データの暗号化を行う。
- 公開かぎの正当性を保証する証明書を発行する。
- 転送すべきデータのダイジェスト版を作成し,電子署名として提供する。
|

|
|
|
【問19】
ある会社の資材担当者が電子メールを取引先へインターネットで配信したところ,取引先から不明なファイルが添付されているとの連絡が入った。資材担当者はファイルを添付した覚えがなく,電子メールソフトのマニュアルを見ても,添付されるとは記載されていないファイルであった。この場合,資材担当者の取るべき行動のうち,適切なものはどれか。
- 送信履歴の添付ファイルを開き,確認する。画面上に見覚えのない画面が表示された場合,送信履歴から送信メールを削除する。
- どのような内容が送信されたのか,添付ファイルを開いて確認してくれるように送信先に依頼する。
- パソコンにデータ破壊などの異常が発生していなければ,問題なしと判断し,そのままにする。
- 連絡を受けた時点で,取引先には,添付ファイルを開かないように依頼し,すぐに自社のセキュリティ対策担当部署に調査を依頼する。
|

|
|
|
【問20】
ユーティリティプログラムの不正な実行によるデータの改ざんや破壊を防止する管理手段のうち,適切なものはどれか。
- システムログの採取
- ソースプログラムと実行プログラムの比較
- データのバックアップ
- ファイルへのアクセス権限の設定
|

|
|
 |