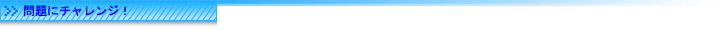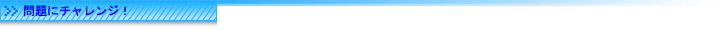|
 |
問題 |
答えを選ぶ |
正否 |
 |
 |
| |
【問1】
既存のシステムのある機能を修正したところ,今まで正常に動作していた機能で異常終了した。不十分であったと考えられるテストはどれか。
- エンドユーザが本稼働前に運用して確認するテスト
- システム要件に定められている機能が,すべて含まれているかどうかを検証するテスト
- 退行していないことを確認するテスト
- 量的な負荷をかけてシステムが業務に耐えられるかどうかを確認するテスト
|

|
|
|
|
| 【問2】
ブラックボックステストを担当することになった。入力項目“年齢”(整数値)の正常データ範囲が15≦年齢≦60であるとき,限界値分析に用いるテストデータとして適切なものはどれか。
|

|
|
|
【問3】
業務システムの開発においては,顧客と開発者,又は開発者同士の意思疎通を図る上で,対象業務に使用される言葉の意味や用法を用語集として整理しておくことが有効である。この用語集の取扱いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 開発着手段階から作成,更新する。
- 開発の最終段階でマニュアル執筆者が作成する。
- 小規模なシステムの場合には不要である。
- 対象業務に関する専門用語だけをまとめる。
|

|
|
|
【問4】
ディジタル動画データの圧縮技術MPEG1の音声部分の圧縮アルゴリズムを使ったもので,インターネット上やポータブルプレーヤでも利用されている音声データの圧縮技術はどれか。
|

|
|
|
【問5】
データベースシステムにおける障害時のリカバリ機能であるロールバックに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 更新後ジャーナルを用いて,トランザクション開始後の障害直前の状態にまでデータを復旧させる。
- 更新後ジャーナルを用いて,トランザクション開始直前の状態にまでデータを復旧させる。
- 更新前ジャーナルを用いて,トランザクション開始後の障害直前の状態にまでデータを復旧させる。
- 更新前ジャーナルを用いて,トランザクション開始直前の状態にまでデータを復旧させる。
|

|
|
|
【問6】
データベースを使用する際,検索中に情報を更新できる機能をもたせるとデータベースの内容に不整合が生じることがある。こうした事態を防ぐための機能として,適切なものはどれか。
|

|
|
|
【問7】
システムヘ追加される新機能に関する事前説明会が開催されることになった。初級システムアドミニストレータのAさんは,システムを利用するすべての人に,この説明会になるべく出席し,意見を交換するように勧めた。Aさんが期待した効果はどれか。
- アルゴリズムの正当性の検証
- 開発コストの低減と開発期間の短縮
- システム開発作業に対するユーザの参画意識の向上
- ホワイトボックステストケースの設計
|

|
|
|
【問8】
パソコン,サーバ,ネットワーク機器などの導入から運用管理までの総費用を示す用語はどれか。
|

|
|
|
【問9】
コンピュータシステムのコストを初期コストとランニングコストに分けるとき,初期コストに含まれるものはどれか。
|

|
|
|
【問10】
システムの運用・管理の観点から,システムライフの終わりと判断するには不適切なものはどれか。
- 新しいバージョンのプログラムに対応できないケースが増えて,利用者の不満の声が大きくなってきた。
- 機能の追加や修正を何度も繰り返したことによって,プログラムが複雑化して,メンテナンス作業が大きな負担になってきた。
- 故障が増えて,メンテナンスパーツの入手にも期間がかかり,修復が遅れるようになってきた。
- 不正なアクセス,プログラムやデータの破壊,パスワードの盗難などが起きるようになってきた。
|

|
|
|
【問11】
システム運用に関する記述のうち,最も適切なものはどれか。
- システム運用に関する問題や障害は,実際に発生してみないと分からない場合が多いので,事前の対策よりも,発生したときに対策を立てる方がよい。
- システム運用を円滑に行うためには,オペレータの権限を強化し,障害時の対応判断をオペレータに任せることが望ましい。
- システム運用を効率的かつ効果的に行うためには,開発部門や利用部門の参加を求めるよりも,運用部門だけで運用テストを行う方がよい。
- システム稼働後でも変更が発生する可能性があるので,変更管理基準をあらかじめ定めておくことが望ましい。
|

|
|
|
【問12】
ワープロの書式に関する記述のうち,タブ機能に関するものはどれか。
- 印刷するとき,文章の上部や下部に印刷される特定の文字列をいう。
- 印刷するとき,用紙の上下左右に設ける余白などの幅のことである。
- 書式を整えるために,カーソルを同じ行のあらかじめ定められたけた位置まで進める機能である。
- 文章の開始位置や行末位置を決めるもので,行頭揃えや行末揃えに使用する。
|

|
|
|
【問13】
データの伝送における暗号技術に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 暗号化及び復号する際のかぎの方式として主に“公開かぎ方式”と“比較かぎ方式”が使用されている。
- データを暗号化して伝送することによって,情報の漏えい及びデータの破壊を防止できる。
- 電子決済や電子マネーでのユーザ認証に使われる電子署名には,公開かぎ方式を使った暗号技術が用いられる。
- 不特定多数の相手とデータを交換するときに適しているのは,共通かぎ方式を使った暗号化である。
|

|
|
|
【問14】
インターネットで公開されているソフトウェアに添付されている電子署名の目的はどれか。
- ソフトウェアが正しく動作することを保証する。
- ソフトウェアの使用を特定の利用者に制限する。
- ソフトウェアの著作者が自分の電子メールアドレスを利用者に知らせる。
- ソフトウェアの内容が改ざんされていないことを確認する。
|

|
|
|
【問15】
公開かぎ暗号方式を採用した電子商取引において,取引当事者から独立した認証局(CA)が作成するものはどれか。
|

|
|
|
【問16】
コンピュータウイルスの一種であるマクロウイルスに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- 実行形式のファイルでメールに添付されて送られるウイルス
- ネットワークで接続されたコンピュータ間を自己複製しながら移動するウイルス
- 複数のウイルスを複合させた新たなウイルス
- ワープロソフトや表計算ソフトのデータファイルに寄生するウイルス
|

|
|
|
【問17】
ノート型パソコンの盗難によるハードディスク内データの漏えいに対処するために,重要なデータの取扱方法として,適切なものはどれか。 |

|
|
|
【問18】
運用中のプログラムを改変し,特定の条件のときに実行される不正な命令を隠しておく手口に対して有効な対策はどれか。
- 一時記憶領域にあるプログラムは,ジョブの終了時に確実に消去する。
- 実行用プログラムのバックアップコピーと本番に使用しているプログラムを定期的に突き合わせて,一致していることを確かめる。
- 全レコードの総合計欄の値が,各レコードのフィールド値を合計した値と一致していることを確認する。
- データの各フィールドにチェックデイジットを付加する。
|

|
|
|
【問19】
“コンピュータウイルス対策基準”において,ウイルスを発見した場合にシステム管理者が行うべき事後対応の項目として,適切なものはどれか
- アクセス履歴を記録し,一定期間保存する。
- ウイルス感染の必要情報を経済産業省が指定する者に届ける。
- システムにインストールされた全ソフトウェアの構成情報を保存する。
- バックアップを行い,データを一定期間保管する。
|

|
|
|
【問20】
経済産業省“ソフトウェア管理ガイドライン”の要求事項のうち,適切なものはどれか。
- ソフトウェア管理責任者が一括して,ソフトウェアのインストールを行うこと
- ソフトウェア使用許諾契約の内容については,そのソフトウェアユーザ全員に周知徹底すること
- ソフトウェアの不正使用を防止する観点から,ソフトウェア管理責任者は,フリーウェアの使用を促進すること
- 法人が保有するコンピュータに個人所有のソフトウェアをインストールして業務で使用することは,資産管理上及び安全上の観点から禁止すること
|

|
|
 |