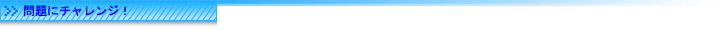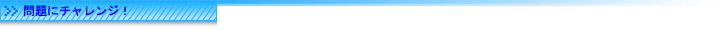|
 |
問題 |
解説 |
 |
 |
| |
【問1】
CD-Rに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- データの書込みは,MOと同様にレーザと磁気を用いる。
- データの書込みはレーザを用い,CDと同様の素材に微小な穴を開ける。
- データの読取りは通常のCD-ROMドライブで行えるが,データの書込みには専用のドライブが必要である。
- 部分的なデータの書換えはできないが,一度ディスクの全データを消去してから再度書き込むことはできる。
|
|
Ans:3 データの読取りは通常のCD-ROMドライブで行えるが,データの書込みには専用のドライブが必要である。
CD-Rの書き込みには,CD-Rドライブ(市販の製品はほとんどがCD-RWも記録できるCD-R/RWドライブ)が必要です。なおCD-ROMの工場生産時の書き込みでは微細なくぼみ(ピット)を作りますが,CD-Rでの書き込みは異なります。 |
|
|
【問2】
スマートメディアの使い方として,最も適切なものはどれか。
- LANカードの通信プログラムを格納するメモリとして使う。
- ターミナルアダプタのファームウェアを格納するメモリとして使う。
- ディジタルカメラの着脱可能な画像記録用メモリとして使う。
- パソコンのBIOSプログラムを格納するメモリとして使う。
|
|
Ans:3 ディジタルカメラの着脱可能な画像記録用メモリとして使う。
スマートメディアは,フラッシュメモリを搭載したメモリカードの一種です。ディジタルカメラの画像記憶用メモリとして用い,カメラからはずしてスマートメディアのリーダに装着することで,パソコンへの画像データの取り込みが可能です。 |
|
【問3】
接続コードを使用せずに,手元のパソコンから,低いパーティションで隔てられた隣のパソコンヘ画像ファイルを転送したい。このとき利用できるインタフェースはどれか。
|
|
Ans:Bluetooth
Bluetoothの通信範囲はクラスで異なりますが10m〜100mで,低いパーティションなら通信は可能でしょう。IrDAは赤外線通信で,物で遮られやすい上に,機器間を数10cmに近づけないと通信できません。 |
|
【問4】
10BASE-Tに用いられるケーブルはどれか。
|
|
Ans:ツイストペアケーブル
10BASE-TのTは,ケーブル仕様としてツイストペアケーブルを意味しています。 |
|
【問5】
2MバイトのビデオRAMをもつパソコンで,フルカラー(約1,670万色:24ビットカラー)を表示させる場合,表示可能な最大サイズ(水平方向画素数×垂直方向画素数)はどれか。
|
|
Ans:800×600
・1:24ビット×640×480/8=921,600バイトで,2MバイトのVRAMに収まります。
・2:24ビット×800×600/8=1,440,000バイトで,2MバイトのVRAMに収まります。
・3:24ビット×1024×768/8=2,359,296バイトで,2MバイトのVRAMに収まりません。
・4:24ビット×1280×1024/8=3,932,160バイトで,2MバイトのVRAMに収まりません。 |
|
【問6】
ハブを用いて10BASE-TのLANを構築し,複数台のパソコンを接続している。ポートが足りなくなり,ハブを増設することになった。このときに留意しなければならない点として,適切なものはどれか。
- 同じポート数をもつハブを増設する必要がある。
- カスケード接続できるハブの段数に制限がある。
- ルータと一緒に増設する必要がある。
- ルータに接続できるハブのポート数に制限がある。
|
|
Ans:2 カスケード接続できるハブの段数に制限がある
10BASE-Tを使うLANでは,カスケード接続できるリピータハブの段数は,最大4段までに制限されています。 |
|
【問7】
LANに接続されている複数のパソコンを,ISDN回線を使って,同時にインターネットに接続したい。これを実現するために不可欠な装置はどれか。
|
|
Ans:ダイヤルアップルータ
ダイヤルアップルータは電話回線に接続して,ダイヤルするなどの通信機能を搭載したルータです。 |
|
【問8】
LANを構築する際に,ルータを導入する利点として,適切なものはどれか。
- 接続された複数のLANのネットワークアドレスを同一にできる。
- 接続されている機器の台数の把握や稼働状況の管理ができる。
- 中継する必要のないデータを識別し,通過を抑止することができる。
- ほかの通信に影響を与えることなく,ノードの増設や移設ができる。
|
|
Ans:3 中継する必要のないデータを識別し,通過を抑止することができる。
ルータは,外側のLAN宛の通信データだけを識別して通します。つまり,中継する必要のない通信データの通過を抑制できます。 |
|
【問9】
DSUの説明として,適切なものはどれか。
- 送受信時にデータビット列の直列・並列変換やエラーチェックを行う。
- ディジタル伝送回線と端末間の信号形式の変換を行う。
- データ通信時にディジタル信号をアナログ信号に変調し,その逆の復調も行う。
- 非ISDN端末をISDNに接続するためのプロトコル変換を行う。
|
|
Ans:2 ディジタル伝送回線と端末間の信号形式の変換を行う。
DSU(Digital Service Unit)はISDN回線の終端制御装置として,BチャネルとDチャネルの通信データを分離・統合したり,各種の回線制御を行います。「端末間の信号形式の変換」はTAが行うものもありますが,消去法からいっても2になります。 |
|
【問10】
記憶媒体の有効利用やバックアップ,配布などの効率化を目的として,複数のファイルを一つにまとめる処理はどれか。
|
|
Ans:アーカイブ
複数のファイルを1つの書庫に変換するソフトを,アーカイバといいます。アーカイバは圧縮処理も行うため,「圧縮/伸張ソフト=アーカイバ」として扱われることが多いです。 |
|
【問11】
分散型システムとホスト集中型システムを比較した説明のうち,最も適切なものはどれか。
- 分散型システムでは,ネットワークやコンピュータヘの不正な侵入を防ぐために,暗号化・認証などホスト集中型システムでは不要な対策が必要になることが多い。
- 分散型システムでは,ホスト集中型システムと異なり,ユーザごとの資源の利用状況を把握したり,ユーザの不正なアクセスを監視したりする必要が生じることが多い。
- 分散型システムは,構成機器だけでなく処理自体も分散されるので,ホスト集中型システムよりもシステム管理が複雑化し,障害時の原因追求に時間がかかることが多い。
- ホスト集中型システムを分散型システムとして再構築すると,ダウンサイジングの効果によって運用・保守コストは低減することが多い。
|
|
Ans:3 分散型システムは,構成機器だけでなく処理自体も分散されるので,ホスト集中型システムよりもシステム管理が複雑化し,障害時の原因追求に時間がかかることが多い。
集中型システムではホストコンピュータを中心に管理すればよいですが,分散処理では複数のコンピュータに分かれているため,原因追及も困難なものになります。 |
|
【問12】
3層クライアントサーバシステムの説明のうち,適切なものはどれか。
- システムを機能的に,Webサーバ,ファイアウォール,クライアントの3階層に分けたシステムである。
- システムを機能的に,アプリケーション,通信,データベースの3階層に分けたシステムである。
- システムを物理的に,メインフレーム,サーバ,クライアントの3階層に分けたシステムである。
- システムを論理的に,プレゼンテーション,ファンクション,データベースの3階層に分けたシステムである。
|
|
Ans:4 システムを論理的に,プレゼンテーション,ファンクション,データベースの3階層に分けたシステムである。
クライアント(プレゼンテーション)とデータベースサーバの間に,中間層のアプリケーションサーバ(ファンクション)を入れた形態です。 |
|
【問13】
新たな情報システムを開発するに当たり,候補となっているコンピュータシステムの性能を評価することにした。この時点で実施が困難なものはどれか。
- 実際の業務データを用いたベンチマークテストによる性能評価
- シミュレーションソフトウェアで稼働状況を再現した性能評
- 平均命令実行時間を基にした性能評価
- 待ち行列を使った処理状況の解析による性能評価
| |
Ans:1 実際の業務データを用いたベンチマークテストによる性能評価
開発前の段階ですから,実際の業務データを開発したシステムで実行することはできません。そのためシステムがほぼ完成した時点から行う,ベンチマークテストの実施は困難です。 |
|
【問14】
パソコンのマルチタスクOS上で表計算ソフトを使用中に,ワープロソフトを起動しようとしたところ,メモリ不足が原因で起動できなかった。根本的な解決策はメモリ増設であるが,それまでの対応として,有効な手段はどれか。
- 仮想メモリの大きさの設定値を増やす。
- 磁気ディスク上の不要なファイルを消去する。
- 接続してある周辺装置を外す。
- ワークシート中の未使用の列は,表示しないようにする。
|
|
Ans:1 仮想メモリの大きさの設定値を増やす。
主記憶メモリの不足ですから,仮想メモリの設定値を変えて大きくとることで解決できます。この点では,1が該当します。しかし仮想メモリはハードディスクの空き領域を,主記憶メモリの一時的な領域として使うため,ハードディスクの空き領域が足りない場合は2で解決できます。題意からすると前者の方がかなっており,まず実施すべき手段であるため,1を正解例とします。 |
|
【問15】
あるシステムにおいて,MTBFとMTTRがともに1.5倍になったとき,アベイラビリティ(稼働率)は何倍になるか。
|
|
Ans:変わらない
コンピュータの全稼働時間は,正常に稼働している時間(の平均がMTBF)と,障害で稼働できない時間(の平均がMTTR)を合わせたものとなります。従って,両方を1.5倍してもMTBFとMTTRの比率は変わらず,稼働率も変わりません。 |
|
【問16】
CATVを利用したインターネット接続に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- CATVでは,1本の線を共有する多数の利用者が同時にアクセスすると,データ伝送速度が低下する。
- CATVの下り方向のデータ伝送速度は,事業者によらず一定である。
- CATVは1方向の送信しかできないので,上り方向には電話網を使用する。
- CATV用のケーブルモデムは,仕様が標準化されている。
|
|
Ans:1 CATVでは,1本の線を共有する多数の利用者が同時にアクセスすると,データ伝送速度が低下する。
CATVでは,局からのケーブルを分岐して,各戸に配線します。そのため上り(利用者→局)側では利用者側で混入したノイズが累積し,下り側に比べて通信速度を低下させる原因となっています。このノイズを,流合雑音といいます。流合雑音が発生することからも分かるように,CATVでは複数の利用者で回線を共有しています。そのため利用者の通信データ量が増えれば,混み合って伝送速度が低下します。 |
|
【問17】
現在広く利用されているIPv4に対し,IPv6の導入によって可能になるものはどれか。
- インターネットの急速な普及によって起きるIPアドレス不足の解消
- 電子メールアドレスやドメイン名での日本語使用
- 光ファイバによる一般家庭からのインターネット接続
- 複数のホストに同時にパケットを配送するマルチキャスト
|
|
Ans:1 インターネットの急速な普及によって起きるIPアドレス不足の解消
IPv4では32ビットのIPアドレスを使っているため,割り当て不足が生じることが懸念されています。IPv6はその問題を解決するために,128ビットのIPアドレスを使用します。 |
|
【問18】
多数の電子メール利用者に対する広告や勧誘などの目的で,受信者の意向とは無関係に短時間のうちに大量に送られ,場合によってはメールサーバのダウンにもつながるものを何と呼ぶか。
|
|
Ans:スパムメール
スパムとは,モンティ・パイソンのコメディの中で連呼したセリフだそうで,それから無意味に大量なものという意味合いで使われています。 |
|
【問19】
文字,静止画,動画,音声,音楽などで表現された情報同士をリンクさせ,そのリンクをたどって次々と関連情報に到達できるようにしたものはどれか。
|
|
Ans:ハイパテキスト
ハイパテキストやその特徴であるリンク機能は,テッド・ネルソンが1960年代に提唱した概念で,それを実用化したものがWWWです。 |
|
【問20】
マルチメディアオーサリングツールの説明として,適切なものはどれか。
- 画像,音声,文字などの素材を組み合わせて,マルチメディアコンテンツを作るためのツールである。
- 画像,音声,文字などのマルチメディア情報を扱うソフトウェアを作成するためのCASEツールである。
- 画像,音声,文字などのマルチメディア情報を検索するためのツールである。
- 画像,音声,文字などのマルチメディアデータベースのスキーマを会話形式で定義するためのツールである。
|
|
Ans:1 画像,音声,文字などの素材を組み合わせて,マルチメディアコンテンツを作るためのツールである。
マルチメディアコンテンツを作るツールで,製品例として,Macromedia社のDirectorがあります。 |
 |