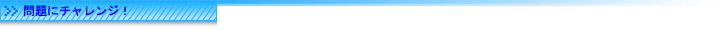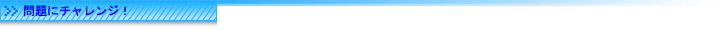|
 |
問題 |
解説 |
 |
 |
 |
【問1】
数多くの数値の加算を行う場合,絶対値の小さなものから順番に計算するとよい。これはどの誤差を抑制する方法を述べたものか。 |
|
Ans:情報落ち
絶対値の小さなものから加算していくということは、計算の対象となる2つの数の絶対値の差が少なくなる、ということである。
絶対値の差が大きな数どおしを計算する時に起こる誤差は、情報落ち、なので答えは「情報落ち」。 |
 |
|
【問2】
スタックに関する記述として,適切なものはどれか
- 最後に格納したデータを最初に取り出すことができる。
- 最初に格納したデータを最初に取り出すことができる。
- 探索キーからアドレスに変換することによって,データを取り出すことができる。
- 優先順位の高いデータを先に取り出すことができる。
|
|
Ans:1.最後に格納したデータを最初に取り出すことができる。
スタックとは値を一時的に退避させておく際に用いられる手法のこと。
イメージとしては、机の上にある本を片付けるために、本をダンボールに次々積んでいく様子に似ている。このようにすると、本を取り出す時には、当然最後に積んだ本から順に取り出さなければならない。(最初に入れた本はダンボールの底にあるので、最初には取り出せない。)
この方式をLIFO(Last-In Fast-Out)後入れ先出し法、と呼ぶ。 |
|
【問3】
未整列の配列A[i](i=1,2,・・・,n)を,次のアルゴリズムで整列する。要素同士の比較回数のオーダを表す式はどれか。
〔アルゴリズム〕 (1)A【1】〜A【n】の中から最小の要素を探し,それをA【1】と交換する。 (2)A【2】〜A【n】の中から最小の要素を探し,それをA【2】と交換する。 (3)同様に,範囲を狭めながら処理を繰り返す。
〔選択肢〕
- O(log2n)
- O(n)
- O(nlog2n)
- O(n2)
|
|
Ans:4.O(n2)
オーダとは、アルゴリズムの性能を示す指標の一つ。大量のデータ(データ数はNとする)を処理する場合、どれくらいの処理が必要になるのかを示す値である。
問題文の整列法は「基本選択法」と呼ばれるもので、このアルゴリズムのオーダはO(n2)で表されることが知られている。 |
|
【問4】
素子の動作は比較的遅いが,集積度を高めることが可能なので,プロセッサや周辺の回路を1個のチップに搭載した大規模LSIを安価に製造でき,プロセッサの主流として広く使用されている半導体はどれか。 |
|
Ans:CMOS
最近の CPU はほぼ全て、CMOS で構成されている。
2.記憶素子。主にメモリに使用されている。
3.、4. いずれもバイポーラ型の素子である。 |
|
【問5】
キャッシュメモリに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- キャッシュメモリのアクセス時間が主記憶と同等でも,主記憶の実効アクセス時間は改善される
- キャッシュメモリの容量と主記憶の実効アクセス時間は,反比例の関係にある
- キャッシュメモリは,プロセッサ内部のレジスタの代替として使用可能である
- 主記憶全域をランダムにアクセスするプログラムでは,キャッシュメモリの効果は低くなる
|
|
Ans:4.主記憶全域をランダムにアクセスするプログラムでは,キャッシュメモリの効果は低くなる
キャッシュメモリはCPU と主記憶の間を取り持ち、速度差を解消するための緩衝記憶装置である。
よって、速度は 【速い】CPU > キャッシュメモリ > 主記憶【遅い】となる。
また、キャッシュメモリは使用頻度の高いデータのみを選んで保管しておくことで処理効率を高めているため、全てのデータが同じ頻度で使用された場合には処理効率は低くなってしまう。 |
|
【問6】
コンピュータの高速化技術の一つであるメモリインタリーブに関する記述として,適切なものはどれか。
- 主記憶と入出力装置,又は主記憶同士のデータの受渡しをCPU経由でなく直接やり取りする方式
- 主記憶にデータを送り出す際に,データをキャッシュに書き込み,キャッシュがあふれたときに主記憶ヘ書き込む方式
- 主記憶のデータの一部をキャッシュにコピーすることによって,レジスタと主記憶とのアクセス速度の差を縮める方式
- 主記憶を複数の独立して動作するグループに分けて,各グループに並列にアクセスする方式
|
|
Ans:4.主記憶を複数の独立して動作するグループに分けて,各グループに並列にアクセスする方式
1.DMA(Direct Memory Access)の説明
2.ライト・バックの説明
3.キャッシュメモリの説明 |
|
【問7】
DVDの大容量化を可能にしている理由のうち,適切なものはどれか。
- 磁気ヘッドの磁化強度を複数もつ
- 磁気ヘッドの磁化方向を複数もつ
- レーザ光線の光度が強い
- レーザ光線の波長が短い
|
|
Ans:4.レーザ光線の波長が短い
DVD は CD に比べ単位面積あたりのデータの記録密度が高い。そのため CD よりも読み取りに使用するレーザの波長が短くなっている。
1.、2.DVDに磁気ヘッドは存在しない。
3.現在のところ、記録容量と光度は無関係。 |
|
【問8】
磁気ディスク装置において,データの管理単位の容量の大小関係として適切なものはどれか。 |
|
Ans:シリンダ>トラック>セクタ
必ず記憶すること。 |
|
【問9】
ポートの空きがないパソコンに,RS-232C インタフェースのモデムを追加接続するときに用いる適切な方法はどれか。
- シリアルインタフェースボードを拡張スロットに装着する
- パラレルインタフェ−スボードを拡張スワットに装着する
- ピン配列を変換するコネクタを介してシリアルポートに接続する
- 分岐用のコネクタを介してパラレルホートに接続する
|
|
Ans:1.シリアルインタフェースボードを拡張スロットに装着する
2.RS-232C はシリアル転送なので誤り。
3.、4.問題文に「ポートには空きがない」と書かれているので誤り。 |
|
【問10】
PDP(プラズマディスプレイパネル)に採用されている発光方式に関する記述として,適切なものはどれか。
- ガス放電に伴う発光を利用する
- 画面の各ドットを薄膜トランジスタで制御する
- 電圧を加えると発光する有機化合物を用いている
- 電子銃から電子ビームを発射し,蛍光体に当てて発光させる
|
|
Ans:1.ガス放電に伴う発光を利用する
プラズマとは雷のような現象で、気体にエネルギーを加えることで人工的に造りだすこともできる。
この技術を応用したものがプラズマディスプレイである。
選択肢の中で、気体が使われているものは 1.の「ガス」のみである。 |
|
【問11】
スワッピングに関する記述として,適切なものはどれか。
- 仮想記憶の構成単位であるページを,主記憶から補助記憶に書き出したり,補助記憶から主記憶に読み込んだりする
- システム資源全体の利用率の向上などのために,主記憶と補助記憶の間でプロセスを単位として領域の内容を交換する
- 主記憶上に分散した空き領域を移動して,連続した大きな空き領域を生成する
- プログラムを機能ごとにモジュールに分割し,実行時に必要なモジュールだけをロードする
|
|
Ans:2.システム資源全体の利用率の向上などのために,主記憶と補助記憶の間でプロセスを単位として領域の内容を交換する
スワッピングとは、容量の小さいメモリを有効に利用するため、メモリ内のデータを一時的にハードディスクなどに「どかしておく」技術のことである。
1.ページングの説明
3.コンパクション(デフラグ)の説明
3.モジュール化の説明 |
|
【問12】
低速の入出力装置やCPUやどの処理効率向上を図るために,入出力データを一時的に磁気ディスク装置に蓄え,CPUや出力装置の空き時間に処理する機能はどれか。 |
|
Ans:スプーリング
キャッシング:よく使われるデータや最近使ったデータを、アクセスの速い記憶装置に置いておくこと。
スラッシング:容量の大きなデータを処理した際に、メモリと仮想記憶の間で頻繁にデータ交換が起きる状態。
ページング:仮想記憶方式の一つ。固定長のページという単位を用いるため、こう呼ばれる。 |
|
【問13】
メモリリークに関する記述として,適切なものはどれか。
- アプリケーションの同時実行数を増やした場合に,主記憶容量が不足し,処理時間のほとんどがページングに費やされ極端なスループットの低下を招くことである
- アプリケーションやOSのバグなどが原因で,動作中に確保した主記憶が解放されないことであり,これが発生すると主記憶中の利用できる部分が減少する
- 実行時のプログラム領域の大きさに制限があるときに,必要になったモジュールを主記憶に取り込む手法である
- 主記憶の内容と補助記憶の内容とを交換する処理のことである
|
|
Ans:2.アプリケーションやOSのバグなどが原因で,動作中に確保した主記憶が解放されないことであり,これが発生すると主記憶中の利用できる部分が減少する
1.スラッシングの説明
3.オーバーレイの説明
4.スワッピングの説明 |
|
【問14】
RASISに関する記述のうち,可用性(アベイラビリティ)に関するものはどれか。 - 機能単位の寿命の範囲内で,一定期間における修理保守に要する平均時間を測定する
- コンピュータシステムにおける問題の判別,診断,修理などを効果的に行う
- コンピュータシステムを必要に応じていつでも使用できる状態に維持する
- 不正なアクセスによって,コンピュータシステムが破壊されたり,データを盗まれたりしないように,防止策を考える
|
|
Ans:3.コンピュータシステムを必要に応じていつでも使用できる状態に維持する
可用性は使用可能性を示し、MTBFを平均故障間隔、MTTRを平均修復時間としたとき、稼働率=MTBF/(MTBF+MTTR)などで計る。 |
|
【問15】
インターネットサービスプロバイダを利用し,存在しない受取人アドレスを指定して電子メールを送信した場合の記述として,適切なものはどれか。
- このようなメールは,インターネット上を転送され続けることになる。このことが,インターネットの通信負荷を増大させており.大きな問題となっている
- このようなメールは,受取人がいないことが確認された時点で,NIC(ネットワークインフォメーションセンタ)によって廃棄される
- このようなメールは自分の契約しているプロバイダのDNSサーバであて先不明と分かるので,ほかのDNSサーバを探しに行くことはない
- このようなメールを送信すると,受取人アドレスが正しくないことが発信人やメールサーバの管理者に通知される
|
|
Ans:4.このようなメールを送信すると,受取人アドレスが正しくないことが発信人やメールサーバの管理者に通知される
1.受取人が存在しない時点で、メール自体はサーバにより破棄される。
2.サーバによって破棄されるのであり、NIC など特定の機関は関係ない。
3.ホスト名が間違っていた場合には正しい。しかし、ユーザID が間違っている場合も考えられ、この場合はほかの DNS サーバを探しに行く場合もある。 |
|
【問16】
再帰的な処理を実現するためには,実行途中の状態を保存しておく必要がある。そのための記憶管理方式として,適切なものはどれか. |
|
Ans:LIFO
再帰的な処理ではABCDEの順でプログラムを呼び出した場合EDCBAの順番に戻っていくのでスタック(LIFO)を用いて管理するのが適当である。 |
|
【問17】
ERPソフトウェアパッケージに関する説明のうち,最も適切なものはどれか。
- 企業のビジネスプロセスの分析が不要なので,比較的容易に導入できる
- 導入後のメンテナンスは,システム部門が担当することが望ましい
- 日本企業のビジネスプロセスを組み込んだ統合化システムソフトウェアである
- ビジネスプロセスの見直しが不可欠であり,社内のコンセンサスと経営者の決断が重要である
|
|
Ans:4.ビジネスプロセスの見直しが不可欠であり,社内のコンセンサスと経営者の決断が重要である
1.ERPパッケージに業務を合わせる必要があるため、ビジネスプロセスの分析が必要である
2.メンテナンスはベンダーにアウトソーシングするのが一般的である
3.ERPは世界標準のビジネスプロセスを採用している。 |
|
【問18】
下流CASEツールが備えている機能はどれか。 |
|
Ans:テスト支援機能
下流CASEツールにはテスト支援機能とプログラム支援機能が含まれる。1.、3.、エはいずれも上流CASEツールの機能である。 |
|
【問19】
E−Rモデルに関する記述として,適切なものはどれか。
- エンティティは特性を表すための属性(アトリビュート)をもつ
- 異なった種類のエンティティ間の関係は,主として状態遷移として表現される
- 一つのエンティティは,インスタンスを一つだけもつ
- 物理的に実在するもの以外は,エンティティとはならない
|
|
Ans:1.エンティティは特性を表すための属性(アトリビュート)をもつ
2.エンティティ間の関係はリレーションシップとして表される。
3.一つとは限らない
4.ひとまとまりの情報として扱えるものであればエンティティになりうる。 |
|
【問20】
モジュール分割を行うときの方法として,モジュール結合度を最も弱くできるものはどれか。
- 一つのモジュールにできるだけ多くの機能を入れる
- ニつのモジュール間で必要なデータ項目だけを引数として渡す
- ほかのモジュールとデータ項目を共有するためにグローバルな領域を使用する
- ほかのモジュールを呼び出すときに,呼び出されたモジュールの論理を制御するための引数を渡す
|
|
Ans:2.ニつのモジュール間で必要なデータ項目だけを引数として渡す
1.モジュール強度に関する説明である。
2.データ結合、3.共通結合、4.制御結合についての説明である、したがってモジュール結合度が最も弱いのは2.である。 |
 |