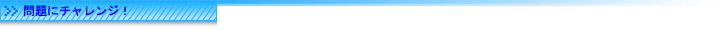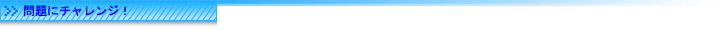|
 |
問題 |
解説 |
 |
 |
| |
【問1】
10進数の0.6875を2進数で表したものはどれか。 |
|
Ans:0.1011
10進数の小数部に2を掛けて、整数部を並べると2進数小数に基数変換できる |
|
|
| 【問2】
数値を2進数で格納するレジスタがある。このレジスタに正の整数xを入れた後、“レジスタの値を2ビット左にシフトして、これにxを加える”操作を行うと、レジスタの値はxの何倍になるか。ここで、シフトによるあふれ(オーバフロー)は、発生しないものとする。 |
|
Ans:5
2ビット左シフトすると2×2=4倍になるので、x×2×2+x=5x。つまり5倍となる。 |
|
【問3】
負数を2の補数で表すとき、8けたの2進数nに対し−nを求める式はどれか、ここで、+は加算を表し、OR、XORは、それぞれビットごとの論理和、排他的論理和を表す。 |
|
Ans:(n XOR 11111111)+00000001
nをビット反転したものに、1を加算すれば2の補数が求まる。2進数nと11111111との排他的論理和をとればnをビット反転したものになるので,これに1を加算すればよい。 |
|
【問4】
浮動小数点演算において、絶対値の大きな数と絶対値の小さな数の加減算を行ったとき、絶対値の小さな数の有効けたの一部又は全部が結果に反映されないことを何というか。 |
|
Ans:情報落ち
1.
は計算等で、無限小数の計算を途中で打ち切ったことによって発生する誤差
2.は絶対値がほぼ等しい同符号の2進数を減算した場合、仮数部の正規化によって有効桁数が少なくなる現象
4.は誤差の値そのもののこと。
|
|
【問5】
10個の節(ノード)からなる次の2分木の各節に、1 から10までの値を一意に対応するように割り振ったとき、節a,bの値の組合せはどれになるか。ここで、各節に割り振る値は、左の子及びその子孫に割り振る値より大きく、右の子及びその子孫に割り振る値より小さくする。 |
|
Ans:a=6,b=7
与えられた2つのルール、
"左の子およびその子孫に割り振られた値より大きい"
"右の子およびその子孫に割り振られた値より小さい"
に従って2分木を完成させればよい。 |
|
【問6】
待ち行列に対する操作を次のとおり定義する。
ENQ n :待ち行列にデータnを挿入する。
DEQ :待ち行列からデータを取り出す。
空の待ち行列に対し、 ENQ 1,ENQ 2,ENQ 3,DEQ,ENQ 4,ENQ 5,DEQ, ENQ 6,DEQ,DEQの操作を行った。次のDEQの操作で取り出される値はどれか。 |
|
Ans:5
待ち行列は「先入先出し(FIFO:First In First Out)」のデータ構造で、以下の(1)から(10)の操作の次にDEQ操作を行なうと、5が取出される。(1)ENQ1 待ち行列に1が挿入される。
(2)ENQ2 待ち行列に2が挿入される。待ち行列の内容は1・2である。
(3)ENQ2 待ち行列に3が挿入される。待ち行列の内容は1・2・3である。
(4)ENQ2 待ち行列に1が挿入される。待ち行列の内容は2・3である。
(5)ENQ2 待ち行列に4が挿入される。待ち行列の内容は2・3・4である。
(6)ENQ2 待ち行列に5が挿入される。待ち行列の内容は2・3・4.5である。
(7)ENQ2 待ち行列に2が挿入される。待ち行列の内容は3・4・5である。
(8)ENQ2 待ち行列に6が挿入される。待ち行列の内容は3・4・5・6である。
(9)ENQ2 待ち行列に3が挿入される。待ち行列の内容は4・5・6である。
(10)ENQ2 待ち行列に4が挿入される。待ち行列の内容は5・6である。 |
|
【問7】
SRAMと比較した場合のDRAMの特徴はどれか。 - SRAMよりも高速なアクセスが実現できる
- データを保持するためのリフレッシュ動作が不要である
- 内部構成が複雑になるので,ビット当たりの単価が高くなる
- ビット当たりの面積を小さくできるので,高集積化に適している
|
|
Ans:4.ビット当たりの面積を小さくできるので,高集積化に適している
1.SRAMの方が高速。SRAMはフリップフロップ回路で構成されているため、高速だが、構造が複雑なため高集積化に向かない。
2.DRAMはリフレッシュ動作が必要。DRAMはコンデンサに電荷が蓄積されているか否かの状態により1または0の情報を記憶するので、時間の経過により電荷が減少し、リフレッシュによる再書込み動作が必要になるため、SRAMより低速だが、構造が単純なため高集積化に向く。
3.
SRAMの方がビット当たりの単価が高い。 |
|
【問8】
CPUのパイプライン処理を有効に機能させるプログラミング方法はどれか
- サブルーチンの数をできるだけ多くする
- 条件によって実行する文が変わるCASE文を多くする
- 分岐命令を少なくする
- メモリアクセス命令を少なくする
|
|
Ans:3.分岐命令を少なくする
パイプライン処理の各ステージの同時実行が出来なくなるケースとして以下のようなケースがある。例えば、分岐命令はパイプライン処理の実行を阻害する要因の1つであり、分岐命令に対しては分岐予測などの技術を用いて回避している。したがって、分岐命令を少なくするのが有効である。また前の命令の演算結果を参照するような命令があると、演算の実効結果待ちが発生するので、このような場合も、パイプライン処理の実行を阻害する要因の1つとなる。 |
|
【問9】
パソコンのCPUのクロック周波数に関する記述のうち、適切なものはどれか。 - クロック周波数は、CPUの命令実行タイミングを制御するので、クロック周波数が高くなるほどパソコンの命令実行速度が向上する
- クロック周波数は、磁気ディスクの回転数にも影響を与えるので、クロック周波数が高くなるほど回転数が高くなり、磁気ディスクの転送速度が向上する
- クロック周波数は、通信速度も制御するので、クロック周波数が高くなるほどLANの通信速度が向上する
- クロック周波数は、パソコンの内部時計の基準となるので、クロック周波数が2倍になると、割込み間隔が1/2になり、リアルタイム処理の処理速度が向上する
|
|
Ans:1.クロック周波数は、CPUの命令実行タイミングを制御するので、クロック周波数が高くなるほどパソコンの命令実行速度が向上する
クロック周波数はCPUの動作に関係するものである。
2.ディスクの回転数は装置そのものの固有の値である。
3.通信速度を制御するものではない。
4.クロック周波数と、内部時計は関係ない。また、リアルタイム処理の割り込み間隔もクロック周波数と直接関係ない。 |
|
【問10】
プロセッサが割込みを発生するのはどの場合か。 - インタリーブ方式によるメモリバンクの切替え完了
- キャッシュメモリに対するヒットミスの発生
- 入出力開始命令の実行
- 浮動小数点演算命令実行によるあふれ(オーバフロー)の発生
|
|
Ans:4.浮動小数点演算命令実行によるあふれ(オーバフロー)の発生
プログラムの演算命令の実行により桁あふれが発生した場合は、ソフトウェア割込みに相当する。 |
|
【問11】
一つのファイルは磁気ディスク上の連続した領域に記録されているのが理想であるといわれる。その理由として、適切なものはどれか。 - 磁気ディスク上にデータの記録されていない部分がなくなり、全領域が利用できる
- ファイルの管理情報を格納する領域が少なくなり、その分ユーザが多く利用できる
- 分割した領域に記録する場合と比較して、読取りエラーが少なくなる
- 連続してデータを読み取る場合、磁気ヘッドの動きが少なくなるので、読取り時間が短くなる
|
|
Ans:4.連続してデータを読み取る場合、磁気ヘッドの動きが少なくなるので、読取り時間が短くなる
磁気ディスク内におけるファイルの記録領域のフラグメンテーションにより、磁気ヘッドを移動するシーク動作が増加し、入出力時間が増大する。そのため1つのファイルを磁気ディスク内の連続領域に格納し直し、シーク動作を減少させて、効率的にアクセスさせる。 |
|
【問12】
500バイトのセクタ8個を1ブロックとして、ブロック単位でファイルの領域を割り当てて管理しているシステムがある。2,000バイト及び9,000バイトのファイルを保存するとき、これら二つのファイルに割り当てられるセクタ数の合計は幾らか。ここで、ディレクトリなどの管理情報が占めるセクタは考慮しないものとする。 |
|
Ans:32
ファイルを割り当てる単位である1ブロックのサイズは500×8=4,000バイトである。
(1)2,000バイトのファイルに対しても1ブロック必要である
(2)9,000バイトのファイルには3ブロック必要である
したがって(1)〜(2)の合計で4ブロック必要になるので、割り当てに必要なセクタ数は、4ブロック×8セクタ/ブロック=32セクタになる。 |
|
【問13】
RAIDに関する記述として、適切なものはどれか。 - 少なくとも2台の磁気ディスク装置を一体化してバックアップの自動化を実現する技術である
- 半導体メモリを使って高速アクセス可能な磁気ディスク装置を仮想的に実現する技術である
- 複数の磁気ディスク装置を使うことによって、記憶装置の高信頼性や高速化を実現する技術である
- ランダムアクセス機能をもつ磁気ディスク装置を実現する技術である
|
|
Ans:3.複数の磁気ディスク装置を使うことによって、記憶装置の高信頼性や高速化を実現する技術である
1.バックアップを自動化する技術ではない。
2.RAMの説明
4.磁気ディスク装置は、基本的にランダムアクセス機能を持っている。 |
|
【問14】
磁化されているディスクの記録膜に、レーザ光を照射して熱した状態で、磁化の方向を変えることによって情報を記録する媒体はどれか。 |
|
Ans:MO
MOは、レーザ光による加熱のもとで磁化し記録する。反対方向の磁界をかけた状態で、記録する部分にだけレーザ光を照射してキュリー点(200度)以上に加熱し、レーザ照射した部分だけを磁界方向に反転させ書込む。 |
|
【問15】
多くの周辺装置を、ハブを使ってツリー状に接続できるインタフェース規格はどれか。 |
|
Ans:USB
USBは、パソコンと低中速系の周辺装置を接続するためのインタフェースである。マウス、キーボード、プリンタ、スキャナ、MOなどをUSBハブ経由で最大127台まで階層的にツリー接続できる。またUSBは、パソコンが起動中でもケーブル着脱ができるホットプラグインや周辺装置を自動認識するプラグアンドプレイにも対応している。 |
|
【問16】
横1,600ドット、縦1,200ドットで、24ビットのカラー情報をもつ画像を撮影できるディジタルカメラがある。このカメラに8Mバイトの記録用メモリを使用すると、何枚の画像を記録できるか。ここで、画像は圧縮しないものとする。 |
|
Ans:1
この画像1枚の容量は、1,600×1,200×24ビット÷8ビット/バイト=5.76Mバイトであるから、8Mバイトの記録用メモリには1枚しか記録できない。 |
|
【問17】
スプーリング機能を使用してプリンタ出力を行うシステムがある。次の条件を満たすためには、スプーリングファイルの容量は少なくとも何Mバイト必要か。
〔条件〕
(1)1ジョブ当たりの印刷データは2Mバイトである
(2)スプーリングファイル上では、データは50%に圧縮される
(3)1時間当たり100ジョブを処理し、処理のばらつきは考慮しなくてよい
(4)最大5時間分の印刷データをスプーリングできる |
|
Ans:500
スプーリングは、主記憶装置と低速の入出力装置の動作に速度ギャップがあり、並行動作における処理の遅れを緩衝するため、高速の補助記憶装置上のスプールファイルに一時出力した後、入出力装置に出力する。これにより、主記憶と入出力装置との並行動作が可能になる。条件(1)から(4)により、スプールファイルの容量を計算すると、2Mバイト×100ジョブ×5時間×0.5=500Mバイトとなる。 |
|
【問18】
あるアプリケーションから見て、OSのオーバヘッドと特定できるものはどれか。 - アプリケーションの割込み処理の実行時間
- タスクスケジューラの実行時間
- ほかのアプリケーションの実行時間
- リエントラントプログラムの実行時間
|
|
Ans:2.タスクスケジューラの実行時間
1,3アプリケーションそのものの時間であり、オーバーヘッドではない。
4.複数のプロセスで同時実行処理可能なプログラムを再入可能であるという。アプリケーションが再入可能プログラムを使用して実行される場合には、そのアプリケーションプログラムの実行時間であり、オーバーヘッドとは限らない。 |
|
【問19】
直接編成ファイルの特徴に関する記述として、適切なものはどれか。 - シーケンシャルアクセスにもランダムアクセスにも適している
- シノニムレコードが発生する可能性がある
- 同一レコードに対して複数のキーを与えることができる
- レコードの挿入はできない
|
|
Ans:2.シノニムレコードが発生する可能性がある
直接編成ファイルでは、データのキーの値を格納先アドレスに変換し、ファイルアクセスを行なう。キーの値により、シノニムが発生する場合もあり、アクセス時間が異なる。また、格納領域に空き領域ができ記録効率が低い。 |
|
【問20】
クライアントサーバシステムの特徴に関する記述のうち、適切なものはどれか。 - クライアントとサーバのOSは、同一種類にする必要がある
- サーバはデータ処理要求を出し、クライアントはその要求を処理する
- サーバは、必要に応じて処理の一部を更に別のサーバに要求するためのクライアント機能をもつことができる
- サーバは、ファイルサーバやプリントサーバなど、機能ごとに別のコンピュータに分ける必要がある
|
|
Ans:3.サーバは、必要に応じて処理の一部を更に別のサーバに要求するためのクライアント機能をもつことができる
1.サーバーとクライアントのOSは同一でなくてもアクセス可能である。
2.クライアントがデータ処理要求を出し、サーバがその要求を処理する。
4.1つのサーバにファイルサーバやプリントサーバなど複数の機能を兼用できる。 |
 |